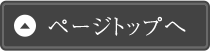3月30日から、七十二候では「雷乃発声(かみなりすなわちこえをはっす)」に入ります。冬の間は鳴りを潜めていた雷が、遠くの空でゴロゴロと鳴りはじめ、春の訪れを告げる頃です。「春雷(しゅんらい)」は「虫出しの雷」とも呼ばれ、冬の間隠れていた虫たちも活動しはじめます。
ところで、雷が鳴るとよく「くわばらくわばら」といいますが、なぜでしょうか?
由来には諸説ありますが、有名なのは、菅原道真が九州の大宰府に左遷されてから落雷被害が増えたので、これは道真のたたりであると考え、落雷を避けるために、道真の領地で落雷のなかった桑原の名を唱えるようになったという説です。菅原道真はのちに天神様・学問の神様と崇められるようになりました。
また、「春告げ鳥」ともいわれるウグイス。「ホーホケキョ」とさえずる美声には春爛漫の趣がありますね。その姿も春らしい「うぐいす餅」のような明るい若草色かと思いきや、実はいたって地味。「梅にうぐいす」とはよくいいますが、梅や桜にやってきて、明るい緑色の姿を見せているのはメジロです。どこで入れ違ってしまったのでしょうか?
ウグイスとメジロの特徴や習性などを比較しながら、そのナゾに迫ります。よく間違われるウグイスとメジロの違いとは?
【暮らしのまつり・遊び】春/ウグイスとメジロ
【季節のめぐりと暦】七十二候
【暮らしのまつり・遊び】春/ウグイスとメジロ
2025年03月30日