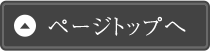1月30日から七十二候の「鶏始乳(にわとりはじめてとやにつく)」になります。春の到来を感じた鶏が鳥屋(とや)に入って卵を産みはじめ・・・
2025年01月30日
七十二候の最終候「鶏始乳」。体の芯から温まる飲み物「葛湯」
2025年01月25日
七十二候「水沢腹堅」。「鷽(うそ)替え神事」で開運祈願
1月25日から七十二候では「水沢腹堅(さわみずこおりつめる)」になります。沢に流れる水さえも凍る厳冬の時期ということで、その光景を・・・
2025年01月20日
寒さ厳しい「大寒」。雪の下から「蕗の薹」が顔を出す頃
1月20日は大寒。冷え込みも厳しく、最も寒い頃です。大寒は二十四節気の最後の節気で、ここを乗り切れば暦の上では春となります。昔は1・・・
2025年01月15日
小正月は、どんど焼きで「正月事じまい」
1月15日は小正月。旧暦の1月15日は立春後の望月(もちづき:満月のこと)にあたり、大昔にこの日を正月としていたなごりで、元日を「・・・
2025年01月13日
人生の節目の佳き日、「成人の日」
1月13日は令和7年度の「成人の日」(1月の第2月曜日)です。新成人の皆様、おめでとうございます。成人の日は「おとなになったことを・・・
2025年01月10日
「鏡開き」で無病息災。「おしるこ」と「ぜんざい」の違いは?
七十二候では、1月10日から「水泉動(しみずあたたかをふくむ)」に入ります。凍った泉の下で水が動きはじめる頃。かすかなあたたかさを・・・
2025年01月07日
「人日の節供」には、七草粥を食べて無病息災
1月7日は「人日(じんじつ)の節供」。"人日"とは文字通り "人の日"という意味です。古代中国では1月7日に「人」の運勢を占い、七・・・
2025年01月05日
寒さが厳しくなる「小寒」。「寒中見舞い」はこの時期に
1月5日は二十四節気の「小寒」。池や川の氷も厚みを増し、寒さが厳しくなる頃です。小寒と大寒を合わせたおよそ1か月を「寒中」「寒の内・・・
2025年01月03日
令和7年は「巳年」。「初詣」も混雑を避けてのんびりと
早くも正月3日となりましたが、初詣にはお出かけになりましたか?もともとはその土地を守る産土神や一族を守る氏神様に新年の挨拶をするも・・・
2025年01月02日
一年を占う「初夢」。抱負をしたためたい「書き初め」
新年を迎えて、「今年はどんな一年になるかしら」と気になりますね。昔の人は「初夢」にその年の運勢が表れるとして、夢の内容で新年の運勢・・・