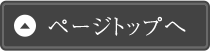6月16日から七十二候では「梅子黄(うめのみきばむ)」。梅の実が黄ばんで熟す頃という意味です。青い梅が次第に黄色みをおび、赤く熟し・・・
2019年06月15日
七十二候「梅子黄」。「嘉祥」にちなむ和菓子の日
2019年06月10日
「入梅」。風情豊かな「和傘」の魅力
6月11日は「入梅」。農作業や暮らしの大切な目安とされていた雑節のひとつです。昔は、芒種の後の最初の壬(みずのえ)の日、立春から1・・・
2019年06月05日
二十四節気「芒種」。夏の風物詩「蚊取り線香」
6月6日は二十四節気の「芒種(ぼうしゅ)」。「芒(のぎ)」とはイネ科植物の穂先にある毛のような部分のことで、芒のある穀物の種をまく・・・
2019年05月31日
「衣替え」は暦が教えてくれる暮らしの知恵
6月の和風月名は「水無月(みなづき)」です。由来は、「無」は「の」の意味があり「水無月」=「水の月」といわれていますが、旧暦の6月・・・
2019年05月30日
七十二候「麦秋至」。日本のパンの生い立ちは?
5月31日から七十二候では「麦秋至(むぎのときいたる)」です。麦畑が黄金色に色づき、収穫時を迎えます。季節は梅雨にさしかかるところ・・・
2019年05月25日
七十二候「紅花栄」。紅花の不思議「半夏の一つ咲き」
5月26日から七十二候では「紅花栄(べにばなさかう)」です。紅花の花が咲きほこる頃という意味ですが、実際にはもう少し遅めの地域が多・・・
2019年05月20日
草木が育つ「小満」。「蚕起食桑」の蚕ってどんな生き物?
5月20日は「小満」。二十四節気のひとつで、陽気が良くなり、草木が成長して茂り、動物や植物にも活気があふれる頃。秋に蒔いた麦の穂も・・・
2019年05月15日
七十二候「竹笋生」。東京の初夏の風物詩、浅草「三社祭」
5月16日からは七十二候の「竹笋生(たけのこしょうず)」。たけのこが出てくる頃という意味です。たけのこは古来よりまっすぐに育つとあ・・・
2019年05月10日
七十二候「蚯蚓出」。ミミズは土作りの立役者
5月11日から七十二候では「蚯蚓出(みみずいずる)」。冬眠していたミミズが地上に出てくる頃という意味です。ミミズは、他の虫たちより・・・
2019年05月05日
二十四節気「立夏」。豊作を願う全国の御田植祭
5月6日は二十四節気の「立夏」。暦の上ではこの日から立秋の前日までが夏です。新緑の季節、田んぼでカエルが鳴き出すのもこの頃。七十二・・・