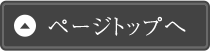11月6日は「一の酉」。鷲神社など、日本武尊(やまとたける)をまつる神社で酉の市が開かれます。酉の市は11月の酉の日に開かれる露天・・・
2017年11月05日
正月迎えの最初の祭り「酉の市」に残る江戸っ子の粋
2017年11月01日
七十二候「楓蔦黄」。平安貴族も楽しんだ「紅葉狩り」
11月2日から七十二候では「楓蔦黄(もみじつたきばむ)」になります。晩秋を彩る山々が美しく紅葉する季節です。実は、日本の紅葉の美し・・・
2017年10月31日
「霜月」の夜空に冴える栗名月。十三夜には栗ごはん
11月の和風月名は「霜月(しもつき)」。文字通り、霜が降る月ということで「霜降月(しもふりつき)」が略されて「霜月」となりました。・・・
2017年10月27日
七十二候「霎時施」。天平の美を間近に見る「正倉院展」
10月28日からは七十二候の「霎時施(こさめときどきふる)」。しとしとと降り続くのではなく、時折、冷たい小雨がぱらぱらと降る頃です・・・
2017年10月22日
二十四節気「霜降」。「山粧う」紅葉の時季
10月23日は二十四節気の「霜降(そうこう)」。「寒露」の次にあたり、露の後は霜ということで気温はさらに低くなってきます。七十二候・・・
2017年10月17日
七十二候「蟋蟀在戸」。商売繁盛を願う「恵比須講」とべったら市
10月18日からは七十二候の「蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり)」。秋の虫が戸口で鳴く頃という意味です。今は「蟋蟀」を「こおろぎ」と読・・・
2017年10月12日
七十二候「菊花開(きくのはなひらく)」。
10月13日からは七十二候の「菊花開(きくのはなひらく)」。菊の花が咲き始める頃です。旧暦では重陽の節供を迎える時期で、菊で長寿を・・・
2017年10月07日
二十四節気「寒露」。「体育の日」に運動会は秋の風物詩
10月8日は二十四節気の「寒露(かんろ)」。草木に冷たい露が降りる頃という意味です。昼間は晴れるとまだ少し暑いときがありますが、朝・・・
2017年10月02日
七十二候「水始涸」。「十五夜」の不思議と「お月見」の楽しみ方
10月3日から七十二候の「水始涸(みずはじめてかるる)」になります。田んぼの水を抜き、稲刈りの準備をする頃。井戸の水が枯れ始める頃・・・
2017年09月30日
「神無月」に神々が大集合。出雲で開かれる重要会議とは?
10月の和風月名は「神無月」。神を祭る月であることから「神の月」とする説が有力とされていて、「無」は「水無月」と同じように、「の」・・・