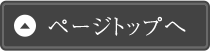11月22日は、二十四節気の「小雪」。「小雪」は、冬とはいえ、まだ雪はさほど多くないという意味です。木々の葉が落ち、山には初雪が舞・・・
2016年11月21日
二十四節気「小雪」。新米をおいしく炊くには?
2016年11月16日
七十二候「金盞香」。寒さに負けず健気に咲く「水仙」
11月17日から、七十二候では「金盞香(きんせんかさく)」になります。「きんせんか」といっても、春に咲くキク科のキンセンカのことで・・・
2016年11月14日
子どもの成長を感謝する「七五三」と「千歳飴」の由来
11月15日は「七五三」。3歳と5歳の男の子、3歳と7歳の女の子の成長に感謝し、神社に参拝して、人生の節目をお祝いする行事です。七・・・
2016年11月11日
七十二候「地始凍」。ひときわ輝く「スーパームーン」とは?
11月12日から、七十二候では地始凍(ちはじめてこおる)になります。大地が凍り始める頃という意味で、霜が降りたり、霜柱が立ったり、・・・
2016年11月08日
収穫の祭り「十日夜」と「亥の子祭り」。歳の瀬を感じる「酉の市」
旧暦の10月10日に行われる収穫祭が「十日夜」です。東日本を中心に行われている行事で、西日本ではよく似た収穫の行事「亥の子祭り」が・・・
2016年11月06日
二十四節気「立冬」。寒い日にはあったか鍋で温まりましょう!
11月7日は「立冬」。二十四節気のひとつで、暦の上ではこの日から立春の前日までが冬になります。木枯らしが吹きはじめ、冬の気配が感じ・・・
2016年10月31日
七十二候「楓蔦黄(もみじつたきばむ)」。紅葉狩りに出かけましょう!
11月の和風月名は「霜月(しもつき)」。文字通り、霜が降る月ということで「霜降月(しもふりつき)」が略されて「霜月」となりました。・・・
2016年10月27日
七十二候「霎時施」。人気を呼ぶ「ハロウィン」の本当の意味
10月28日からは七十二候の「霎時施(こさめときどきふる)」。しとしとと降り続くのではなく、時折、冷たい小雨がぱらぱらと降る頃です・・・
2016年10月22日
二十四節気「霜降」。紅葉が進み「山粧う(やまよそおう)」時季です。
10月23日は二十四節気の「霜降(そうこう)」になります。「寒露」の次にあたり、露の後は霜ということで気温はさらに低くなってきます・・・
2016年10月17日
七十二候「蟋蟀在戸」。商売繁盛を願う「恵比須講」とべったら市
10月18日からは七十二候の「蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり)」。秋の虫が戸口で鳴く頃という意味です。今は「蟋蟀」を「こおろぎ」と読・・・