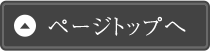8月15日はお盆。各地で様々なお盆の行事が行われていることでしょう。お盆といえば盆踊り。日暮れ時、「ドーンドーンカッカッカ」と威勢・・・
2015年08月14日
楽しいだけじゃない、なぜか切ない「盆踊り」の理由。
2015年08月12日
七十二候「寒蝉鳴」。夏の風物詩「蝉時雨」にも秋の気配。
8月13日から5日間は、七十二候では「寒蝉鳴(ひぐらしなく/かんせんなく)」の期間です。「寒蝉」とは秋を告げる蝉のことで、蜩(ひぐ・・・
2015年08月07日
8月8日は「立秋」。打ち水で涼しい風を呼び込みましょう!
8月8日は「立秋」。二十四節気のひとつで、この日から立冬の前日までが暦の上では秋となります。とはいえまだまだ暑い盛りなので、「暦の・・・
2015年08月01日
夏の睡魔を吹き飛ばせ!東北三大祭りの起源は「眠り流し」
8月2日からは七十二候の「大雨時行(たいうときどきふる)」です。空がにわかに曇り夕立になったりする頃。ひと雨降った後は少しだけ涼し・・・
2015年07月31日
8月1日は八朔。「田の実の節供」と頼みの風習
8月の和風月名は「葉月(はづき)」。葉の落ちる月で「葉落月(はおちづき)」、それが転じて「葉月」になったという説が有力ですが、「葉・・・
2015年07月27日
暑さに負けない!「暑気払い」で元気になるビールの飲み方は?
七十二候では、7月28日から「土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし)」になります。土がじっとりとして蒸し暑くなる頃。蒸し暑いことを「・・・
2015年07月22日
花火大会の掛け声はなぜ「かぎや~」「たまや~」というの?
7月23日から二十四節気の「大暑」。最も暑さが厳しいころという意味です。七十二候では、「桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ)」に入・・・
2015年07月19日
土用といえば?鰻だけじゃない「う」のつくもので夏バテ知らず!
土用といえば夏の土用を思い浮かべることが多いですが、実は土用は四季ごとにあり、立春、立夏、立秋、立冬前の18日間(または19日間)・・・
2015年07月17日
七十二候「鷹乃学習」。鷹は意外と身近な猛禽類?
7月18日から22日までは七十二候の「鷹乃学習(たかすなわちがくしゅうす)」。鷹の子が飛ぶ技を覚え、巣立ちを迎える頃です。日本で鷹・・・
2015年07月12日
「お盆」は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」?意外なことばの意味と由来
7月13日から5日間が七十二候の「蓮始開(はすはじめてひらく)」。蓮の花が咲き始める頃という意味ですが、蓮の花は7月~8月にかけて・・・