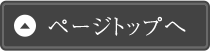菊は、桜と並んで日本を代表する花です。薬草として中国から日本に伝えられると上流階級の人々の間で人気となり、平安時代には「菊の節供」ともいわれる「重陽の節供」が宮中で行われ、菊を愛でながら、華やかな「菊花の宴」が行われていました。邪気を払う力があるとされた菊は、古来より日本人に親しまれ、発展してきました。
■和菊の特徴と種類
中国伝来の菊は日本で観賞用に改良を重ねられ、発展したのが「和菊」です。花の大きさによって「大菊」「中菊」「小菊」などに分類され、鑑賞のための仕立て方にも工夫があります。
大菊:花の直径は20cm位にもなります。周りの余分なつぼみを摘み取り、一輪だけを大きく育てます。花の形状から「厚物」「管物」「広物」などがあり、「三本仕立て」「だるま作り」「福助作り」などに用いられます。平らに咲く広物の「一文字」は、花びらの数が菊の御紋と同じ16枚が理想とされているそうです。
中菊:花は9~18cmほどで、「仏花」や切り花として一般に使われます。江戸菊、嵯峨菊、肥後菊などの「古典菊」もこの分類に入ります。
小菊:花が5cm弱。室内の飾りや、菊人形などに用いられます。
■和菊の仕立て方
菊花展などを見るなら、ぜひ菊の仕立て方も押さえておきましょう。ただ美しいというだけではなく、その高度な栽培技術に感動を覚えるでしょう。
・大菊の仕立て
三本仕立て:大菊の最も基本的な仕立て方です。1本の苗を摘芯して3本の枝を伸ばし、3つの花を咲かせたもの。
だるま作り:三本仕立ての小型版で、草丈は40~60㎝ほど。小さく丸いフォルムからだるまの名前がつきました。
福助作り:1本仕立てで、だるま作りよりさらに小さく草丈を40㎝以内に仕立てたもの。花は大輪なので頭でっかちになり、福助のような姿になることからこの名前がつきました。
千輪作り:1本の苗を何回も摘芯をくり返して枝数を増やし、1株で600輪もの花を咲かせる作り方。ドーム状に隙間なく整然と花が並ぶ姿は圧巻です。
・小菊の仕立て
懸崖(けんがい)作り:盆栽樹形のひとつで、摘芯をくり返して木の先端が鉢より下に垂れ下がった形に仕立てます。
菊人形:歴史的シーンや人気ドラマの1シーンなどを菊の花の衣装を着た人形で表現するもの。シーンに合わせて建てこんだ人形の胴体にあたる枠組みにヒノキの葉を貼り、根のついた菊の花を止めていき、色や柄を表します。
■菊花展・菊まつり
切り花は一年中出回っていますが、秋には丹精を込めた和菊を鑑賞できる「菊花展」「菊まつり」などが全国で開催されます。菊の花だけでなく菊人形が飾られる場合も多く、福島県二本松市の「二本松の菊人形」、福井県越前市の「たけふ菊人形」などが有名です。また、「日本菊花全国大会」のように、菊の品評会も各地で行われています。
こちらもあわせてご覧ください。
【暮らしを彩る年中行事】重陽 菊の節供
【暮らしを彩る年中行事】重陽 菊づくし
2018年10月10日