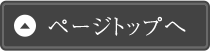「春告げ鳥」ともいわれるウグイス。「ホーホケキョ」とさえずる美声には春爛漫の趣がありますね。その姿も春らしい「うぐいす餅」のような明るい若草色かと思いきや、実はいたって地味。「梅にうぐいす」とはよくいいますが、梅や桜にやってきて、明るい緑色の姿を見せているのはメジロです。よく間違われるウグイスとメジロの違いとは?
■これはウグイス?それとも?
花札の「梅にうぐいす」の札には、紅梅の枝には背の緑色も鮮やかな小鳥がとまっています。そして、和菓子の「うぐいす餅」は青黄な粉をまとった緑色、「うぐいす餡」も青豌豆を使ったきれいな緑色の餡です。こうなるとウグイスは明るい緑色の鳥だと思えてきますね。でも、実際は緑色というより少し灰色がかった渋い色をしています。
実際に梅や桜の花が咲き、その枝をちょんちょんと飛び回る明るい緑色のかわいい鳥をよく見るとメジロです。どこで入れ違ってしまったのでしょうか?
■ウグイスとメジロの見た目チェック
では、実際のウグイスとはどんな姿をしているのでしょう。
色の違いは前述の通りで、ウグイスのオスの体長は約15cm、メスはやや小さく13cm位でやや細身。メジロは、体長は10〜12㎝くらいで、ふっくらとした姿をしています。
そして、ウグイスの目の上には、眉班と呼ばれる眉毛のような白い模様が入っています。
メジロはその名の通り、目の周りに真っ白な縁取りがあります。
見ればはっきり違いが分かります。
■ウグイスとメジロのさえずりチェック
ウグイスといえば「ホーホケキョ」。透明でよく響く美声です。これは繁殖期のオスだけの「さえずり」といわれます。メスへの求愛や縄張りを示すために鳴くといわれています。春先は人里で鳴いていますが、その後は巣作りのために山の方へと移動していきます。巣作りの季節、「ケキョケキョケキョ......」という鳴き声は「鶯の谷渡」と呼ばれ警戒の意味があるといわれています。繁殖期が終わった秋冬の季節には「チャッ チャッ」という鳴き声を出しています。
このようにさえずりはよく聞かれるのに、姿を見せることはあまりありません。高らかなさえずりに反してウグイスは警戒心が強いといわれています。
これに反し、メジロは、春先になるとよく見かけられるようになり、「チーチー」「ピーピー」などとさえずります。
■ウグイスとメジロの食事チェック
ウグイスもメジロも雑食性の野鳥ですが、食べ物の好みに違いがあります。
ウグイスは警戒心が強いので、身を隠せる藪などの場所を好み、昆虫などの虫を主な餌としています。
メジロは甘い物が好きで、果物や花の蜜などが好み。くちばしも細くとがって、花の蜜を吸いやすい形をしています。早春では梅や椿の花にやってくるのでその姿がよく見られるというわけです。
■「梅にうぐいす」の本当の意味
本当によく見られるのは「梅にメジロ」ですが、「梅にうぐいす」といわれるようになったのは、「梅」は春一番に咲きはじめ、「ウグイス」は春の訪れ告げる「春告鳥」ともいわれて、共に親しまれたからでしょう。「梅にうぐいす」は「取り合わせがよい二つのもの、美しく調和するもの」の例えとして使われます。春を待ちわびる日本人の理想のイメージから生まれた取り合わせなのです。
■メジロにまつわる「目白押し」
「梅に来ているのはメジロなのに......」となんとなく無視されてしまった感のあるメジロですが、ちゃんとメジロが登場する慣用句もあります。それが「目白押し」。メジロは複数で行動することが多く、枝に身を寄せ合ってとまる習性があります。そのギュッとくっつきあった様子から、大勢の人が集まってひしめいている様子や、物事が集中してあることを「目白押し」といいます。
また、余談ですが「メグロ」という小鳥もいます。大きさはメジロと同じくらいで、背から尾にかけては緑色で、胸から腹は黄色です。目の周りにはメジロのような白いリングがありますが、その周りに三角形をした黒色斑があります。小笠原諸島の固有種でここにだけ生息しており世界でも珍しい鳥ですが、近い将来野生での絶滅の危険性が高いとされています。
2025年03月30日