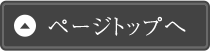春は貝の季節です。多くの貝は夏に産卵するので、春から栄養を蓄え始めます。そのため身がふっくらとして味も良くなる季節なのです。特にアサリやハマグリなどの二枚貝がおいしい盛りです。春はまた、潮干狩りなどの磯遊びのシーズンです。旬の貝を獲ったり、いろいろな料理で食べたり、春の貝は楽しみ方がたくさんあります。
■潮干狩りで定番のアサリ(浅蜊)
どこの干潟でも手軽に採れたアサリ。アサリという名は、たくさん獲れるので「漁る(あさる)」からついたという説や、「あ」は浅い場所、「さり」は砂利(砂地)に棲んでいるからという説もあります。
潮干狩りで狙うなら生まれて2〜3年目の3~4cm程度の大きさ のものが、身が柔らかくおいしいそうです。いまは国産の量は減り、外国産が多く出回っています。
アサリの砂抜きの方法などはこちらをご覧ください。
【暮らしのまつり・遊び】春/潮干狩り(リンク)
■ひな祭りには欠かせないハマグリ(蛤)
ハマグリは殻長が約8cm前後、重量が100g程度まで成長します。
国産では鹿島灘や三重県・桑名などが有名です。「桑名の焼き蛤」は東海道名物で、「その手は桑名の焼き蛤」という慣用句は、「その手は食わない」の「くわな」を「桑名」にかけ、桑名名物の焼き蛤をつけて、「うまいこと言ってもその手にはだまされないよ」というシャレです。
旧暦の3月は磯遊びの季節だったので、ひな祭りのお吸い物にも欠かせません。 蛤などの二枚貝は、対の貝殻しか絶対に合わないことから、幸せな結婚を願う気持ちが込められています。
■栄養の宝庫シジミ(蜆)
シジミは、淡水と海水が混じり合う汽水域などに生息しており、通常の大きさは2~3cmくらい。
汽水湖といわれる島根県の宍道湖はシジミの産地として有名で、大きさはやや小さいもののうまみが強いのが特徴です。
シジミは栄養も豊富。特にオルニチンを多く含むので肝臓の働きを助け、疲労回復にも良いといわれます。シジミ汁にするとシジミのエキスをしっかりとれるのでおすすめです。
■旬が年に2回あるホタテガイ(帆立貝)
ホタテの旬は夏と冬の年2回。春の産卵が終わり成長期にあたる5月から8月は、プランクトンをたくさん食べて貝柱がどんどん大きくなるので、貝柱が太く大きく、甘みがあって濃厚な味を楽しめます。12月から3月の冬場は、産卵前の卵や白子がおいしい季節です。
ホタテは養殖がほとんどで、北海道、青森県、岩手県、宮城県が主な産地です。大きさはさまざまですが殻径が20cmほどにもなる大きな二枚貝です。
■姿が面白い高級食材のミルガイ(海松貝)
ミルガイは水管が大きく発達していて、主に食されるのは水管部分。殻長15cm、殻高9cm程度ですが、常に貝殻が開いて大きな水管が飛び出した姿です。
一般的にはミルガイと呼ばれていますが、正式名称は「ミルクイ」。その水管に「ミル(海松)」という海藻が付いていることがあり、水管が引っ込むときにミルを食べているように見えることから「ミルクイ(海松食)」と名付けられたそうです。
日本全国の海に生息していますが、漁獲量が少ないため大変高級な食材で、一般に出回っているのはミルガイによく似た「ナミガイ」。これらを区別するために、ミルガイは「本ミル」「黒ミル」、ナミガイは白っぽいので「白ミル」と呼び分けることもあります。
■高級な寿司ネタの一つアカガイ(赤貝)
アカガイは、貝をあけると身の色が赤いのでアカガイと呼ばれます。大きさは殻長10~12㎝ほどで、甘味が強いのが特徴です。
宮城県名取市閖上(ゆりあげ)のアカガイは、「閖上赤貝」と呼ばれる高級ブランドアカガイです。ほかにも三陸、愛知県、三重県、長崎県などでも獲られていますが現在は全体的に漁獲量が非常に少なく、中国産や韓国産が多く出回っています。
■ホッキガイ(北寄貝)
ホッキガイの正式名称は、ウバガイ(姥貝)で、殻の長さ10cm、殻の高さも8cm前後と大型。北海道苫小牧が漁獲高日本一で特産品になっています。
寿司ネタやサラダなどで見かけるホッキ貝は、赤からピンクのきれいな色をしていますが、生の身は薄い紫褐色。湯通しすることで鮮やかな赤みのある色になります。甘みがあり、柔らかめな食感が特徴です。
2025年04月04日